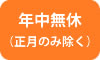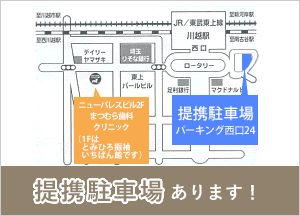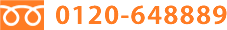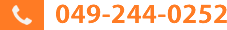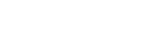歯や歯周組織に異常が見られないにも関わらず、歯に痛みを感じる状態を「非歯原性歯痛」といいます。歯の痛みを訴えて受診した人の約3%が、非歯原性歯痛だといわれています。
① 筋・筋膜性歯痛
筋・筋膜性歯痛は、咀嚼筋(食べ物を噛むときに使う筋肉)や首の筋肉、これらの筋肉を覆う筋膜の痛みが原因で起こる関連痛です。関連痛とは、痛みの原因から離れた場所が痛くなることをいいます。
②神経障害性歯痛
神経障害性歯痛は、神経障害性の疼痛が原因で起こる歯の痛みで、主に2つのタイプに分けられます。
ひとつは発作性で、三叉神経の痛みが原因で起こる激痛です。
もうひとつは持続性で、代表的な原因として帯状ほう疹や帯状ほう疹の後遺症による神経痛があります。神経周囲の炎症や腫瘍、骨折によって、神経が障害されることが原因となる場合もあります。
③神経血管性歯痛
頭痛の関連痛として起こる痛みです。
④上顎洞性歯痛
上顎の骨の中にある副鼻腔の空洞に、炎症や腫瘍があり起こる関連痛です。
⑤心臓性歯痛
狭心症や心筋梗塞、心膜炎などの心臓の病気が原因で起こる関連痛です。
⑥精神疾患、心理・社会的要因による歯痛
不安や気分が落ち込む抑うつといった、心理社会的要因が背景にあって起こる歯の痛みです。
⑦突発性歯痛
さまざまな検査をしても原因がわからない歯の痛みを特発性歯痛と呼びます。
⑧その他様々な疾患による歯痛
巨細胞性動脈炎や悪性リンパ腫、肺がんなど、病気が原因で起こる歯の痛みです。
非歯原性歯痛の診断をするには、まずむし歯や歯周病などの問題がないかを、問診や視診、レントゲン写真などで調べます。歯や歯周組織に問題がない場合は、8つの原因にあてはまる症状がないか、詳しい問診や触診、場合によってはCTやMRIなどの検査をして鑑別します。